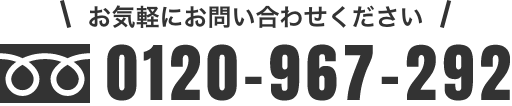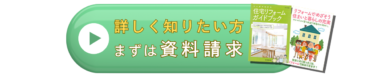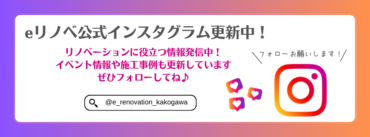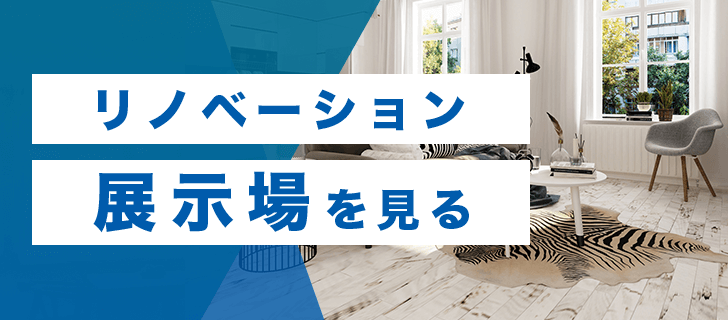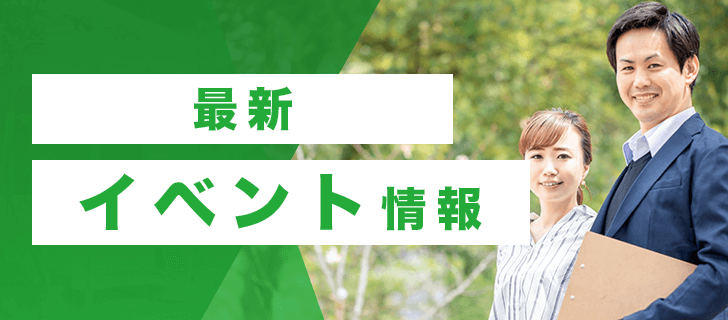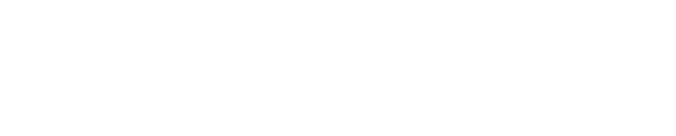ご自宅の大規模リフォームや、ご両親が住む実家のフルリノベーション。計画を進める中で「親から資金を援助してもらう」ケースもあれば、逆に「子が費用を負担して実家を改修し、二世帯で同居する」ケースもあるでしょう。
どちらのパターンでも、その「資金援助」が思わぬ「贈与税」の対象となり、後で多額の税金を納めることになっては本末転倒です。
一方で、国の制度を正しく理解して活用すれば、最大1,000万円もの資金援助を非課税で受けられたり、税務上のリスクを合法的に回避したりすることが可能です。この記事では、一軒家リフォーム専門家の視点から、どちらのパターンであっても税金の不安を解消し、安心して理想の住まいづくりを進めるための知識を徹底解説します。
「年間110万円の壁」贈与税の基本ルール

親から子へ、あるいは子から親へ。リフォームの資金援助の形は様々ですが、どちらのパターンにも共通して立ちはだかるのが「贈与税」の問題です。この基本的なルールを理解していないと、良かれと思った援助が原因で、後日、税務署から思わぬ課税通知が届く事態になりかねません。
数百万円単位の資金が動く大規模リフォームだからこそ、まずはこの税金の仕組みを正確に確認しておきましょう。
贈与税とは?「もらった人」が納める税金
贈与税は、個人から財産をもらった時、その「もらった人(受贈者)」に課税される税金です。
①親から子が資金援助を受けたら、「子」が納税義務者
②子が親名義の実家を改修したら、家の修理費用を親が援助を受けたとみなされ「親」が納税義務者とみなされる可能性
があります。この認識の違いが、後のトラブルの元になりがちです。
基礎控除「年間110万円」を超えると申告が必要
贈与税には「暦年課税」という仕組みがあり、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除額)を超えると、その超えた部分に対して贈与税がかかります。数百万円単位の資金が動く大規模リフォームでは、この110万円の壁は簡単に超えてしまうため、特別な対策が必須となるのです。
【親から子へ】資金援助を受ける場合

親御様から資金援助を受けて、ご自身(子世帯)が所有する家をリフォームするケースです。これは贈与税の対策において、最もシンプルで国の支援制度も手厚く用意されているパターンと言えます。
後述する「住宅取得等資金贈与の特例」を最大限に活用できるため、計画の自由度も高まります。ここでは、その強力な非課税制度について詳しく見ていきましょう。
最大の武器!「住宅取得等資金贈与の特例」で最大1,000万円非課税に
親(または祖父母)から、子や孫が自分名義の家を新築・取得・リフォームするための資金贈与を受けた場合に、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になる、非常に強力な制度です。
2025年10月現在、この特例の非課税限度額は以下のようになっています。
- 省エネ等住宅(※)の場合:1,000万円
- 上記以外の一般住宅の場合:500万円
※省エネ等住宅とは、「断熱等性能等級4以上」や「耐震等級2以上」など、一定の住宅性能を満たす家屋のことです。
なぜ「大規模リフォーム」こそが特例を最大限活かせるのか?
この制度の恩恵を最大化(=1,000万円の非課税枠)しようとすると、必然的に「大規模リフォーム」が最適解となります。その理由は以下の2点です。
1,「省エネ等住宅」の基準を満たしやすいから
1,000万円の枠を得るための「省エネ等住宅」の基準は、単なる水回りの交換といった小規模なリフォームではまず達成できません。壁・床・天井への断熱材の充填、高性能な窓への交換、耐震性の向上といった、家全体の性能を根本から見直す「大規模リフォーム」や「フルリノベーション」を行うことで、初めてこの基準をクリアできます。
2,特例の対象となる工事要件を満たせるから
この特例は、どんなリフォームにも使えるわけではありません。対象となる工事は「増改築等」と定められており、例えば「工事費用が100万円以上」であることや、「耐震・断熱・バリアフリー」など、定められた工事内容であることが求められます。これらも、一軒家全体を手掛ける大規模リフォームであれば、問題なく満たすことができます。
特例利用の主な条件と注意点
・もらう人(受贈者)の条件: 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上、合計所得が2,000万円以下、など。
・贈与者の条件: 直系尊属(父母または祖父母)。
・建物の条件: リフォーム後の床面積が40㎡以上240㎡以下であること、など。
・スケジュールの条件: 贈与を受けた年の翌年3月15日までにリフォーム工事を完了し、居住を開始すること。
・申告の条件: 贈与税がゼロになる場合でも、必ず税務署への申告が必要です。これを忘れると特例は適用されず、多額の税金(追徴課税)が発生します。
【子から親へ】資金援助する場合

二世帯同居や将来を見据え、親御様が所有するご実家(親名義)を、子世帯が費用を負担して大規模リフォームするケースです。これは非常に多いパターンですが、税務上の大きな落とし穴が潜んでいます。
「良かれと思って」行った資金援助が、意図せず「子から親への贈与」とみなされ、親御様に多額の贈与税が課税されるリスクがあるため、綿密な対策が求められます。
最大の落とし穴!「子から親への贈与」とみなされるリスク
親が住む実家(親名義)を、子が自分たちの資金(例:1,000万円)で大規模リフォームするとどうなるでしょう。
この場合、子は「親名義の財産(家)」の価値を高めるために1,000万円を支出したことになり、「子から親への贈与」とみなされる可能性が非常に高いです。
この場合、親が「もらった側」として贈与税(1,000万円 – 110万円 = 890万円が課税対象)を支払う義務を負うかもしれません。
子から親では「住宅取得等資金贈与の特例」は使えない
前述の「住宅取得等資金贈与の特例」は、あくまで「子や孫が自分名義の家を取得・リフォームする」ための制度です。「親名義の家」をリフォームする費用には適用できません。この違いを理解していないと、計画が根本から崩れてしまいます。
【重要】贈与税を回避する3つの解決策
この「子から親への贈与」リスクを回避し、安心して大規模リフォームを進めるには、工事契約前に以下の対策を講じる必要があります。
解決策1:リフォーム前に「名義」を子に変更する(贈与・売買)
最も根本的な解決策です。リフォーム前に実家そのものを親から子へ「贈与」または「売買」し、家の名義を子に移します。
メリット: 家が子名義になるため、子が堂々とリフォーム費用を出せます。さらに、親からの援助があれば「パターン①」の非課税特例も使えるようになります。
デメリット: 家の評価額(土地・建物)に対して、贈与税または不動産取得税・登記費用がかかります。
解決策2:工事の出資割合に応じて「共有名義」にする
現実的で最も多く採られる方法です。リフォームの出資割合に応じて、家の名義を「親と子の共有名義」に変更する登記を行います。
例: 元の家の評価額が500万円(親持分)、子が1,500万円を出して大規模リフォームした場合、家の価値は合計2,000万円になります。この時、親持分4分の1、子持分4分の3という形で「共有持分登記」をします。
メリット: 子が出資した分だけ、正当に子の財産(持分)となるため、贈与税はかかりません。
デメリット: 将来、相続が発生した際に権利関係が複雑になる可能性があるため、他の兄弟姉妹への事前説明が重要です。
解決策3:親子間の「金銭消費貸借契約(借用書)」を結ぶ
子が親にリフォーム資金を「貸した」という形をとる方法です。
メリット: 名義変更などの手間がかからず、すぐ実行できます。
デメリット: 親が子に返済する義務が生じます。返済実績がないと、結局は贈与(名ばかり貸付)とみなされるリスクがあります。金利や返済期間を明記した正式な契約書を作成し、銀行振込などで返済の記録を残す必要があります。
非課税枠が使えない場合の「相続時精算課税制度」

「大規模リフォームで2,000万円の援助を受けたい」「親から実家そのものを贈与される」など、前述の非課税特例だけでは枠が足りない、あるいは適用できないケースもあるでしょう。
このような多額の贈与に対応するため、もう一つの選択肢として「相続時精算課税制度」が用意されています。これは税金を先送りする制度であり、その仕組みと活用法を解説します。
2,500万円まで「一旦」非課税になる制度
「相続時精算課税制度」は、原則60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与において、累計2,500万円までの贈与税を非課税にできる制度です。
ただし、これは「税金を先送りにする」制度であり、贈与した親が亡くなった時、この2,500万円は相続財産に加算されて相続税が計算されます。
親から子への贈与での使い方:
「住宅取得等資金贈与の特例(最大1,000万円)」を優先的に使い、それでも足りない部分についてこの制度(最大2,500万円)を併用します。
子から親へのリスク回避での使い方:
解決策1で「実家そのものを親から子へ贈与する」際に、家の評価額が高額な場合、この制度を使って贈与税の支払いを一旦免除(先送り)するために活用できます。
まとめ

リフォームの資金計画、特に親子間のお金が動く場合は、税金の知識が不可欠です。
親から援助を受けるなら、非課税枠が最大になる「省エネ・耐震性能向上」を伴う大規模リフォームが最も賢明です。
子が実家を援助するなら、必ず工事の契約前に「名義変更」や「共有持分登記」といった対策を講じなければなりません。
どちらのパターンであっても、ご家族の状況によって最適な答えは異なります。ご計画の際は、税理士への相談と並行して、この非課税特例の要件を満たす高性能なリフォームプランや、二世帯住宅化の複雑な条件整理を熟知した、私たちのような一軒家リフォームの専門家へぜひご相談ください。
断熱2倍・耐震2倍・収納2倍!
リノベーション・リフォームならeリノベ!
施工対象エリア「加古川市、明石市、姫路市、高砂市、播磨町、稲美町」
それ以外のエリアの方もお問い合わせください。
現状調査・資金計画・設計・施工・アフターサービスなどを一環してサポート!
品質の高い住まいをご提供いたします。
◎リノベーションモデルハウスで実際に体感しませんか?
実際のリノベーションを体感できるモデルハウスを見学できます。
事前の見学予約でQUOカードもプレゼント!
リフォームについての勉強会も開催しておりますので、ぜひご来場ください!!
◎リノベーションに役に立つ資料を差し上げています!
「リノベーションの最初の一歩はどうしたら良い?」
そんな悩みを解決する、資料を差し上げています。
資料請求後のしつこいセールスはありません!
ぜひ資料請求をしてください。
◎公式instagramではリノベーションに役立つ情報を発信中!
リノベーションに役立つ情報や、リノベーションの豆知識
eリノベのイベント情報等発信中!
リフォーム・リノベーションをお考えの方はぜひフォローして下さいね♪
◎楽しいイベント開催中!
◎施工事例も紹介しています!
最後まで読んでいただきありがとうございました♪